筋原性疾患と神経原性疾患
筋原性疾患と神経原性疾患
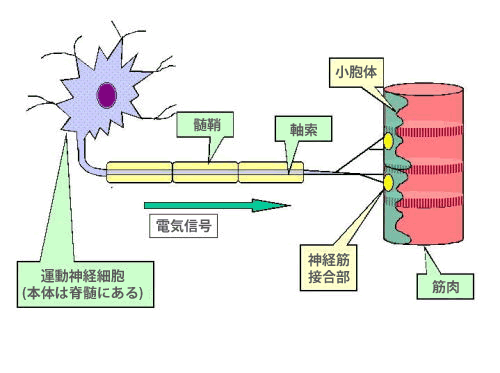
脊髄前角から運動神経までを運動単位といいます。
筋肉への信号は電気信号ですが神経細胞の軸索と言う枝を通ります。軸索には髄鞘というくびれのあるケースに入っていますが、このケースがあると信号がより早く伝わります(跳躍伝導)。
この電気信号は神経筋接合部というところで筋細胞の細胞膜を経て筋細胞の中の小胞体に伝わります。すると小胞体からカルシウムが細胞内に流出し筋肉の収縮を引き起こすのです。
いわゆる筋疾患と言われる病気は筋原性疾患と神経原性疾患に区別されます。
神経原性疾患は運動単位のうち運動神経細胞から神経筋接合部までのどこかが障害される病気を指します。
筋原性疾患はその名のとおり筋肉自体が障害される病気を指します。
神経原性疾患には運動神経細胞が変性していく脊髄性筋萎縮症、髄鞘や軸索が変性するシャルコ・マリー・トゥース病、神経筋接合部の障害による重症筋無力症があります。筋原性疾患には筋ジストロフィーやミオパチーが含まれます。